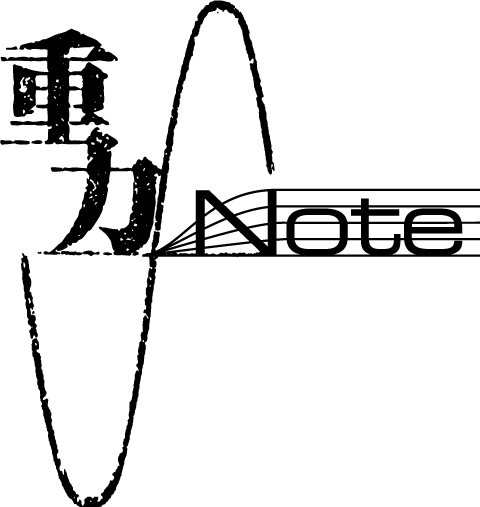▷Project
重力/Noteの活動に継続的に参加している俳優たちによる自主企画。
平井光子による一人芝居、2012年秋より創作に関わっていた永井彩子(現:ながいさやこ)が演出を担当した。
RAFT主催企画【文学+-×÷】芥川龍之介編に参加作品。
▷Concept
『芋粥』の主人公五位が持つ「芋粥に飽かむ」という願望は、現実感のない夢のようなものであったが、彼の生を支えるものであった。願望が現実になることで、むしろこの支えが損なわれる様子が 『芋粥』では描かれている。
『芋粥』に限らず、芥川は他者を鋭く見ることで人間の本質を暴きだすことを常としている。しかし、芥川が暴きだしている他者の現実は、芥川にとって他人のものであり、フィクションである。彼はその芸術論の中で、芸術と生活は相反すると述べているが、他者に眼を向け書き記すという「芸術」行為自体が、芥川にとっての芋粥なのではないだろうか。晩年、芥川は自身を題材にすることで、自分を眼差すこととなる。そのとき目に映るのは、彼を取り巻く飽和した現実だったのではないだろうか。
『芋粥』を上演することで、芥川の、延いては観客の眼差しの暴力性を顕在化する。
「虚構」が前提である演劇に対し、既存の視座に切れ込みを入れるドキュメンタリー的な手法を試みることで、現実が拮抗する歪な作品の創造に挑戦する。






会場 RAFT
原作 芥川 龍之介
出演 平井 光子
構成・演出 永井 彩子
照明操作 来住 真太
音響操作 伊藤 幸江
原案協力 井上 美香
制作 小林 由佳 本多 萌恵
芸術監督 鹿島 将介
主催 NPO法人らふと


▷フライヤー掲載文
私が芥川龍之介を初めて読んだのは、中学生の頃、新潮文庫の『羅生門・鼻』だった。
そのときの印象は、とにかく毛穴。茹でた鼻の毛穴から白い固まりがにゅぅっと出てくる様や、羅生門の下人が弄るニキビ、老婆が死人の髪の毛を一本一本抜く姿など、毛穴ひとつひとつに人間の執着や業が詰め込まれている気がして、ひどく醜悪に感じた。そして同時に、とにかく自分の顔の油やニキビが気になった。
この感じは、今でも時々他人と顔をつき合わせた際に気まずさや羞恥心となって現れる。
毛穴から這い出る自我のひとつひとつを、芥川は見逃してくれない。
「芋粥に飽かむ。」という一言は、ニキビともまた違った自我の露呈だ。顔にニキビができればニキビのことを始終考えてしまうが、芋粥は、むしろ実現を考えないから固執する。
芋粥は夢だ。ピントを調整しながら夢の細部を観察すると、時として欲望は蛇行し、グニャリとゆがむ。
無数の細部に囲まれて生活を送る私たちは、それらを無視することも、夢みることもままならず、眠りまでも浸食されている。
劇場という切り取られた空間の中で、日常の細部を呼び起こし、見ることの暴力性や俗悪さを浮き彫りにする。
芋粥はもう必要ないのか……?
永井彩子

▷当日パンフレット挨拶文
はじめまして、今回『芋粥』の構成•演出を担当させていただきました、永井彩子と申します。
原作の『芋粥』は、本来ならば記録に残らないほど地味な男が、実は芋粥をお腹いっぱい食べることを糧に毎日生きている、ということがポイントに描かれています。芥川龍之介は他者を事細かに見ることで人間の本質を暴きだすことを得意としていますが、『芋粥』でもこの平凡な男の欲望を無理やりに切り開いていくことで、男の生のありかたを根本的に変容させてしまいます。他者と出会い、その顔をじっくりと見たことで、男は変わってしまった。夢にまでみた芋粥を、一口も食べられなくなるほどに。
夢だけを見て他人を気にせずのらりくらりと生きることは確かに楽しいし、うらやましい。そして人間関係が広がれば広がるほど、他者の数だけ、それに対峙する自分の顔が増えていき、その複雑さに吐き気がすることもしばしばです。しかし、それを我慢して、毎朝部屋の扉を開けて外に出つづけていることでしか、人は進めません。
本日はご来場いただきまことにありがとうございます。どうぞ最後までお付き合いください。
永井 彩子
▷芸術監督の挨拶文
去年から仙台でWSや滞在制作をする機会にめぐまれているのだけれど、よく「演出家はどうやって育つのか?」と質問を受けたりする。これにはなかなか返答に窮していて、むしろ私が知りたいくらいなのだが、苦しまぎれながらも「とにかく共同体から孤立すること」と答えるようにしている。妄想癖やら不思議ちゃんといった個性としてではなく、共同作業を方向づけながらも常にそれを外側から見つめる眼差しが、つまり他者としてのイヤな視線をむける自分を保つ必要が演出にはある。
ところで、永井彩子という存在は、これまで私の稽古場において《違和感》を口にしてはなりふり構わず進行を止めるという、いい意味でイヤな他者だった。今回、紆余曲折を経て劇団としての新たな展開を担ってもらう一方、彼女が持つ様々な可能性を観客の皆さんとともに吟味できたらと思う。今日はお立会いいただき、ありがとうございます。
鹿島 将介
Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.