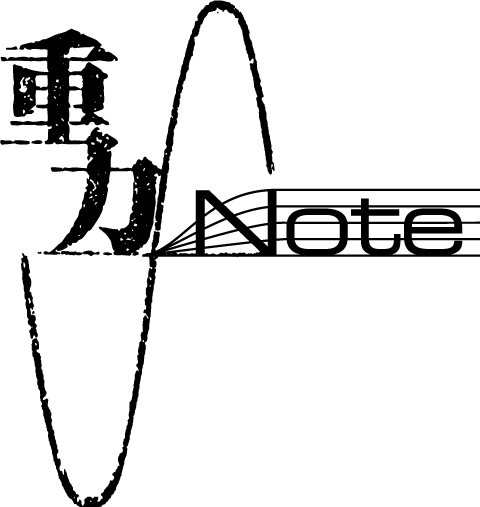▷演出助手・飛田ニケによる記録(画像・イラスト©︎飛田ニケ)
7/14(Fri)
稽古初参加@事務所。出演者三人の経歴とかはそんなによく知らないが、身体的になんとなくキャラっぽく見える。3人という人数もあるだろう。平井の口に、立本が指を入れていて、それを見る牧の構図が印象的だった。俳優が身体をとおして、見ているものや、観客との距離感を超えて、空間を揺すっているようなときが見ていて面白いときかもしれない……スクラップ・ビルド的な……

7/17(Mon),19(Wed),
この戯曲は、〈わたし〉が、旅をしながら、現在なのか回想なのかびみょうな文体で語るモノローグがベースとなって進行し、ときおりメキシコ演劇の父である〈佐野碩〉のような人物が介入してくる。〈わたし〉の旅は、自分探しすれすれだが、そうもならず、自分のルーツをもとめていろいろな土地を巡っていく。物語(?)のはじめ、〈わたし〉は東京のあるビルの一室で目を覚ます……

7/24(Tue),
この頃の稽古は、やっぱり戯曲の文体と、身体の方向性を模索する作業をしている。チューニング。/テクストを発語する俳優はテクストをなにとして扱っているのか?/今回の作品のコンセプトをぶらさずに、だけどそのなかで即興的に演技を重ねることが必要になるだろう。/歴史にアクセスしたがることとたえず他者にさらされ続けるを得ないことのあいだを逡巡する個。/植木等のような無責任と責任のあいだ?/観客はのぞきをするような感じ?/フォルムではなくぐにゃぐにゃと流動的な身体。/路上streetの風景と最終的にひとりじゃないうんぬん……

7/28(Fri),
この上演における常態を探るような稽古。立ち戻る場所というような言い方もされた。立本が「正解がわからない」と言う。鹿島がそれに答える。というようなやりとり。戯曲は素材でしかなくて、そこにも書かれていないようなものを立ち上げなくてはならない。〈見えないもの〉を扱うということらしい。見えないものが結果的に痕跡として残ってしまうような……。『+51 アビアシオン,サンボルハ』の冒頭には、こう書かれている。(俳優のみが演ずることができる)。ちょっと茶化しているような気もするけど。

7/31(Mon),
逡巡。立ちすくむこと。立本の娘さんが生まれた。ので立本さんはおやすみだった。『+51 アビアシオン,サンボルハ』には、佐野碩という、メキシコ演劇の父が登場する。彼は、もう死んでいるので、幽霊?のようなものとして登場するのだが、〈わたし〉という主人公?の妄想のような人物かもしれない。じつは立本が、その台詞を発語するのだが、かれが稽古にいないと、よりその不在によって、幽霊的なものが立体的になる。いないほうがいいというわけではなくて、その不在の立体化というか、質感はとても面白かった。

8/2(Wed),
今回は、演技の即興性が重要で、しかし即興だけでやると「演技がグズグズになる」だろうから、そこここに振付のように動きを決める部分を俳優が考えて、調整するという演技になるそう。だから冒頭部分を念入りに、確かめないと、作品のタッチが上手く定まらない。ということで、冒頭の〈わたし〉の語りを繰り返し試していく。最初、東京から始まるのだが、上演される劇場は、横浜で、大方の観客は東京から横浜に来る事になるから、東京→横浜→東京みたいになるのだろうか。横浜港。劇場はWHARF(波止場)。サンボルハへの右往左往、みたいなことかしら……

8/3-8/6@KINOSAKI,
この期間、城崎へ出かけていたので稽古へは参加できず。観光ではないのだが、ほぼ観光。劇場のある観光地。ただ、ぼくは旅先で、なにをしていいのかわからなくて、ぶらぶらと歩きまくる、みたいなことが多い。夏なのでほとんど熱中症になりかけながら、さまよって、たまに写真を撮る。名所を回るみたいなことをすると、人が多すぎてちょっと難しい。だけど観光客よりも、住んでる人びとよりもっと、情報の少ない土地を歩き回るということはどういうことなんだろうか……。ヘミングウェイの『日はまた昇る』の不能者ジェイクのようなやるせない退屈も、観光客の楽しみ足りうるのだろうか……

8/9(Wed),
稽古は、広めの畳の部屋で。この日、今後のクリエーションを転換するような大発明?があった。くわしくはひかえるので、上演に来てもらえたらいいなと思いますが、三人の俳優が、不思議な共同体をつくりながら、観客へゆるく、全開で語ることができるような空間が出現した。その間、ぼくと鹿島は、爆笑しながら見守ることになった。この発明は、この作品を、〈現代演劇の身体論〉として見ることを可能にするだろう。すこぶる現代的な身体の在り方を提示することができるだろう、と思う。こんなにはっきりと、ラディカルに、政治的に、暴力的に、身体の二重性を暴露してしまうなんて……と興奮してしまった。今後、もっとスリリングな駆け引きが見られたら……と思う。

8/12(Sat),
『+51 アビアシオン,サンボルハ』には、メタ演劇的な部分が強く、演劇批評家が出てきたりする。稽古はそこらへんを中心に。平井が演劇批評家のテクストを発語するのだけど、演出家の鹿島と彼女の対話がおもしろくて(ちょっと失礼かも)、いろいろメモしてある。テクストは、批評家が夢のなかで、沖縄の離島、久高島にいるのだが、宗教的な体験を語るというもの。彼女のコンセプトは「夢と死と神」。ひとを埋葬し、久高島を創り、イースター島のモアイのように立ち、グーグルアースのような視点で世界を見る。演出家は具体性を求めて聞き返すのだが、俳優は、身体ありきの思考で演技を考えているので、あまり噛み合わない対話。この戯曲の俳優の身体とはどういうものだろう。ただやっぱり身体の政治性がはっきりと見える瞬間がぼくには一番おもしろいような……

8/14(Mon),
テキストの意味を身体によってずらすことで、意味を拡張していく(テキストを聴かせる)/身体感覚のはっきりとした(ルールがある、リズム感?)発語の中で非意味的に音楽的にずらすことで生まれる享楽/出ハケをしないでほかの俳優の発語を蓄積して発語の動機にする。/神里雄大のリズム感→シだと思ってるはず。文体がつくるリズムから逃れるためには? 韻律みたいなもの/「日本国籍を強調しすぎた鬼っ子」/観客にひらきすぎず、閉じすぎずのバリエーション(距離感の)
ぼくのノート、ほぼママ。
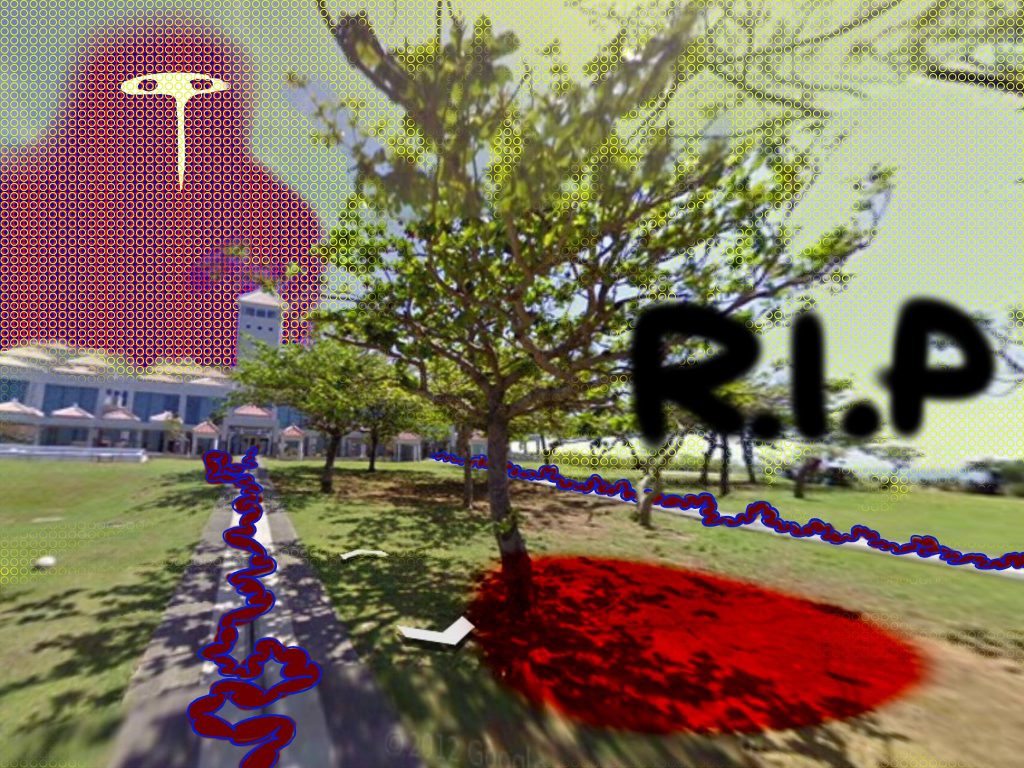
8/16(Wed),
重力/Noteの演劇作品は、リアリズムではない。ハイパーリアルなナチュラリズムとも違うし、直截なスペクタクルも避けて、それでも残った演劇性を俳優の身体で構成していく。この廃墟のような(P・ブルックがいう「何もない空間」のニュートラルな地点の不/可能性から)演劇を、現代演劇として位置づけるなら、かれらは戯曲や劇場や演技そのものも、限りなく0から立ち上げなければならないだろう。既存の制度からの逸脱というよりも、あらゆる諸要素との関係性を、0から制度化しなければならない。しかしこのとき、0が無限遠点のように宙吊りにされた概念でしかないとして、上演では、俳優や空間や時間、そして観客さえも、廃墟を抱えざるを得ない。忘却に忘却を重ねたうえに、「なにもない空間」を立ち上げるとすれば、それは廃墟だろう。いま・こことのあらゆる持続が絶たれた場所で、なにもかもを接続しなおす身振りから、演劇を再考するための演劇。その意味で、重力/Noteの演劇的地平はオルタナティブであり、コンテンポラリーであると言えるだろう。(なんとなくの試論。)

8/18(Fri),
演技のキャラ化みたいな問題がある。身体や発語の強度を高くするとそれは起こる。そうなると自ずとテンポや、スタイルが決定されていき、即興的なおもしろさや、観客と俳優の距離感が閉塞しがちになる。かといって観客や環境に演技をひらきすぎると、集中力が散漫になり、というか観客もなんとなくだらだら~っと演技をまなざすことになる。ようは塩梅なのだが、演技の設計というのは、そういう巨視的な部分と微視的な部分を併せ持っているので、俳優たちはとてもタイヘンそうだな~と思う。なにしろ戯曲は、設計図ではなく、それを自分の想像力や妄想や即興から見つけるしかないから。

8/21(Mon),
若葉町WHARFでの稽古。ぼくはWHARFに初めて来て、みんな言うけれど、若葉町周辺がとてもおもしろい。あたりにあるお店も多国籍料理が多く、歩いている人も、アジア系の外国からきた人が多い。こういう町にある劇場は、どういう場所になるのだろう? WHARFは、今年新しくできた劇場だが、泊まることもできる。願わくは、客席が、いろいろな言語で賑わうような場所になったら面白いだろうと思う。そして今回の上演は、そういうこととセットで楽しめるかもしれない。日本人とはだれか?ということなのかしら……

8/22(Tue),
演技をくりかえすとはどういうことだろうか? もちろん演劇は繰り返す。それは上演のレベルでも、そうだし、稽古でも、なんども反復する。ぼくは俳優の経験もあるから、なんとなく分かるが、同じことをくりかえすという心持ちで俳優は、演技をしていない。しかし、それでもやっぱり何度もやってると反復に耐えられず、演技がかちかちに固まってしまうような状態が訪れる。それは、即興性というレベルで面白くなくなってしまうのだが、問題の一つには、演技のハードルの問題があると言える。設計された演技が安易であったりすると、俳優もやっぱり飽きてしまう。そのうえで、演技は、複雑である必要がある。そうでなければやっぱり初めて見るひとも、やってるほうも心底、それに飽きているということになってしまうのだろう。飽きることは、演劇の制度に敷衍してももうちょっと考えられるかもしれない。劇団とか……

8/24(Thu),
『+51 アビアシオン,サンボルハ』は、モノローグを中心に構成されている戯曲だ。牧が〈わたし〉のモノローグを、稽古している時に、ふとこれは映画のワンショットの持続に似ているんじゃないかと思った。どこかへ向かい歩いている被写体を、追いかけるカメラ。被写体もカメラも動いているが、割らずに、延々長回し。この長回しというのは、現実の時間にけっこう近いわけで、リアリティが生まれる。持続したひとつの時間の流れを感じることができる。演劇は、現前でなされるから、ひとつの時間なのだけど、俳優は、発語と身体で、うまいこと時間を飛ばしたりする。だけど、ここでのモノローグは、意味上の時間こそばんばん飛んでいくが、身体とのズレによって、独特な緊張を孕んだ持続した時間をつくりだす。それは、ワンショットの、どこにいくのかわからない、持続に似ているように感じられる。あのだらだらと持続した緊張。あしぶみと弛緩した笑み。かれらは誰なのか?
この破壊的なモノローグのじゃじゃ馬ならしが、この作品作りの大きな課題だといえる。
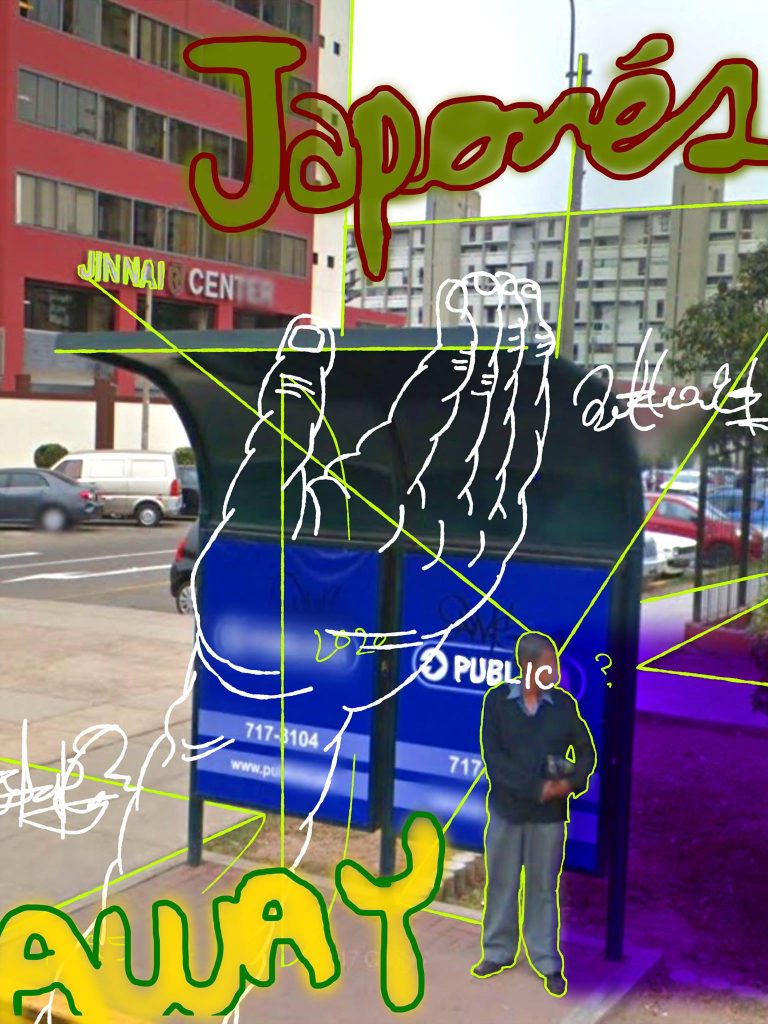
8/29(Tue),
WHARFでの通しを観る。美術や照明や音響が、入ってきたので、稽古よりかなりクリアに観られる。そのうえでかなり変な?作品だなーと、ラフに笑いながら観ていた。
ところで、神里雄大は、この作品を作・演出家として上演している。作・演出家とはなんだろうか? 日本では比較的よくみられる形態だが、台本を書くのと、それを演出するのを一手に担う役割だ。そして、この戯曲に関しては、「わたしとはだれか?」というテーマ性もあり、ちょっと精神分析のようなところが、あるのかもしれない……。そのうえで、書き手と作り手が隔てられていると、そこの部分を批評することも必要になるだろう。作・演出家とはだれなのか? このテクストに現れる、怒りや悪意のようなものが、裏返しのように自己嫌悪のように感じられるときが、今回の上演にはあり、それがその先で、わたしたちはだれなのか? ということにツッコミを入れてくれることを期待している。そういうひろがりもあるかもしれないと半ば妄想しつつ……

Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.