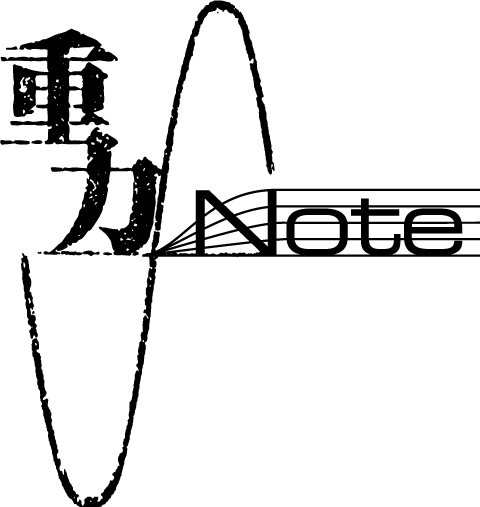今は存在しないけれど、存在するにちがいない何ものかを生産する―
▷Project
ノーベル文学賞作家であり、いまなおドイツ語圏において問題作を発表し続けているエルフリーデ・イェリネクが1988年に発表した戯曲『雲。家。』。
たえず繰り返されていく「わたしたち」を前にどんな思考が呼び覚まされるのか?
またそれらは現在の日本に生きる人々にとってどのように響くものなのか?
いまに生きる「わたしたち」の可能性を探っていく。
フェスティバル/トーキョー12公募プログラム参加作品
▷Concept
ページを繰っても繰っても台詞が終わらない。ついに「自分で何を言っているのかわからなくなる」と俳優がボヤく。数多の引用とイメージが編み込まれた言葉の濁流の中で、それを口にする方も聞く方も所在がわからなくなっていく——そんなイェリネクのテキストを読むたびに突きつけられるのは、「言葉を耳にし、口にするとはどういうことなのか?」という問いだ。
解釈、解体、脱構築など、演出家の職能を説明する言葉は、テキストの一貫した《物語》に対する批評的な関わり方において有効だった。だが、もはや《物語》への関与という技術が成立しないテキストを前に、演出家は一体何ができるのか? 彼女の残した言葉は、あらゆるものの足場を揺るがす。
「今は存在しないけれど、存在するにちがいない何ものかを生産する」とイェリネクが語るとき、そこには誰も出会うことの叶わなかった《演劇》が発見されることへ期待が宿っている。まるで生まれる前から埋葬されてしまった死体のような《演劇》を内包するテキスト。それを読む/聞くことの発明、それ自体が演出なのだ。執拗に冗長さを必要とした衝動への眼差し、痕跡として残された言葉/歴史への聞き方ひとつひとつを俳優とともに存在させていくことが、テキストと観客の出会いを創出することに繋がる。
ところで、言葉が氾濫した舞台の上から俳優は一体どんな《顔》をして観客を眼差すのだろうか? そのとき、観客はどんな《顔》をしているのだろうか?














会場 シアターグリーン BIG TREE THEATER
原作 エルフリーデ・イェリネク
翻訳 林 立騎
出演 稲垣 干城 井上 美香 瀧腰 教寛 立本 雄一郎 平井 光子 邸木 夕佳
構成・演出 鹿島 将介
舞台監督 中原 和樹
音楽 後藤 浩明
音響 佐藤 武紀
照明 木藤 歩
衣裳 富永 美夏
舞台美術・宣伝美術 青木 祐輔
ドラマトゥルク 關 智子
英語案内 伊藤 羊子
演出助手 佐々木 琢
記録 永井 彩子
当日受付 宮島 久美 山田 真美 山方
制作補佐 藤田 侑加 秦 朝弓
制作統括 増永 紋美
協力 アマヤドリ 酒井著作権事務所
宣伝協力 有限会社ネビュラエクストラサポート
後援 オーストリア大使館 オーストリア文化フォーラム
共催 フェスティバル/トーキョー
主催 重力/Note
上演時間 約100分


《ことば》の重心がウツロウ時間のなかで
唐突だけれども覚悟してほしい。この『雲。家。』の上演では、550回以上の《わたしたち》を耳にすることになります。時間に換算すると1回が1.5秒くらいなので、上演時間のうち約14分のあいだは《わたしたち》という語句に付き合うことになるわけです。この執拗に繰り返される《わたしたち》の応酬それ自体が、「今は存在しないけれど、存在するにちがいない何ものかを生産する」と語るイェリネクの、誰も出会うことの叶わなかった《演劇》へと繋がるすべとなるはずです。
ところで《わたしたち》という言葉は、口にしてみると不思議な響きを伴う言葉で、俳優たちには「何かを代表して喋らなきゃいけない感じがする」そうです。では、それを聞く方はどうかというと、どこからどこまでを指した《わたしたち》なのかとか、また自分の内に滞る感覚の似姿を求めながらそれを聞いてしまうといったような、変な体感があります。登場人物の誰かと誰かがスッタモンダを開帳してくれる《演劇》とは、もう全く違う感じ。しかもドイツの話だったりするから、さらにコトは複雑です。
《わたしたち》という言葉について考えたとき、あるポルトガルの詩人の顔が浮かびます。彼は、ひたすら《わたし》で在り続けようとし、ついには自分の身体のなかに生じた感覚ひとつひとつにすら個々の人格として(ご丁寧なことに詳細な履歴書まで添えて)、それぞれに《わたし》と名づけていきました。こうして数々の《わたし/異名》を生み出していったフェルナンド・ペソアの孤独な作業には、彼の生きた20世紀という《ことば》の重心がウツロウ時節における「名づけの精神史」としての苦節/屈折が伺い知れる。それは思春期にありがちの自分探しではない、どこまでも《わたし》の、当事者としての域に留まって生きようとする、生の所在を問う作業だと思います。
さて、イェリネクです。ペソアの無数の《わたし》と、イェリネクの無数の《わたしたち》が屹立している場所は、案外近いのではないか――今回これが作業仮説になっているのですが、こうした問いを孕んだテクストは、決してトレンドに付き合うようなものではありません。アクチュアリティなんかない、リアリティなんかない。あるのは、この世界の地中に向かって深く彫り込まれた言葉があるだけです。彼女がよく使う言葉――《死者の子供たち》のために、すでに埋められた言葉が《わたしたち》のために。
鹿島 将介

▷当日パンフレット掲載の挨拶文
「おいおい、ドイツ民族の歴史なんて知ったこっちゃないよ」 これは開演後しばらくしてから皆さんの頭に去来する――かもしれない心の呟き。ここではテレビで見聞きしたようなトピックスも なければ、韓流ドラマのような情熱的な恋愛もありません。ひたすら何者かによって口にされたドイツ民族や大地にまつわる話が繰 り返される。それらを繋いでいる《わたしたち》という言葉だけが、僅かに耳慣れたものとして手渡されます。しかも 550 回以上も 執拗なまでに。果たして、そのひとつひとつをどこまで記憶できるというのでしょうか? 演劇というジャンルがこれまでに蓄積し てきた形式の大半は、限られた時間のなかで如何に記憶されるかという、言わばどうにかして他者の記憶に留まろうと画策すること でした。つまり他者の記憶を占めようとするわけですが、そもそも思い出されるためにはまず最初に忘却されなくてはなりません。 どうもイェリネクのテクストには、過剰なまでの意味とイメージの濁流としてある一方で、忘却への衝動と想起への衝動が同居して いるように思います。まずは早く忘れて、それから早く思い出して……と。まるで書き記した言葉よりも、その消尽と想起の運動 自体を追い求めていたかのように。同時にますます浮かび上がる意味の廃墟性。こうした言葉の在り方の中で、ドイツ民族の歴史を さらに遡った根源的なものを私たちは眼差せるのかもしれません。
本日はご来場いただき、ありがとうございます。イェリネクが言葉を尽くしたように、演劇でどこまで尽くすことができたか、最後までご覧いただけると幸いです。
鹿島 将介
▷ドラマトゥルク關智子の挨拶文(当日パンフレット掲載)
『雲。家。』はおよそ戯曲とは思えないような、まるで散文詩か小説であるかのように書かれています。しかし、確かに演劇のために 書かれたテクストなのです。では、この作品は演劇の何を前提としているのでしょうか。
その答えの一つとして、俳優の存在が挙げられます。このテクストでは、登場人物が人間かそうでないのか、生きているのか死んで いるのかも定かではなく、そもそも登場人物と呼ぶのが相応しくない存在によって言葉が語られています。そのため稽古では俳優が、 言葉を自分のものとして語ることはあまりせずに、「舌語り」(自分のものではない言葉を話している状態)になっているように見えま した。彼女は語れないことを語っていたのです。 この俳優を目にし、イタリアの哲学者であるアガンベンが「証言」と呼んだものの ことを考えました。彼はアウシュヴィッツにおける語りについて論じ、語ることができないということ によってのみ語ることができることを「証言」と呼んでいます。この「証言」との奇妙な一致は、イェリネク作品の上演に対して、一 つの光を投げかけるのではないでしょうか。
イェリネクのテクストを上演すること、またその上演における俳優の存在は、「私たちは何を語ることができるのか?」(F/T11)と いう問いに対する一つの答えとなっています。つまり、「言葉のかなたへ」(F/T12)行き、語ることができなくなったことによって語 られるものこそ、語ることができる唯一のもの、アガンベンが「証言」と呼んだものであり、3.11 以降 の<わたしたち>が感じるものであり、イェリネクのテクストが俳優を通して与えるものだと思うのです。
▷ドラマトゥルク關智子とのやりとり(抜粋)
暴力について
關 8月31日の稽古で少し話題に上った暴力についてですが、多分干城さんが言ったのはパロールとエクリチュールの問題、ことばそのものの問題な気がしています。つまり、何か「ことば」にしてしまうことで失われていくものがあって、しかし「ことば」で表すしかない、何かを失わせるその力を「暴力的」と表現したのではないでしょうか(違ったらすみません)。このことに関してはデリダの『エクリチュールと差異』で論じていたように思いますが、手元に資料がない上に理解に不安があるために、コメントだけで失礼します。
参考になるか分かりませんがエスリンの暴力論を抜粋して掲載します。M. エスリンは、当時のイギリス演劇の中で増えつつあった暴力的描写について論じ、演劇が持つ暴力について述べています。
暴力にはなにが含まれているか? 真の暴力性とはなにか? 私がだれかの頭をなぐるとすれば、わたしのしたこととはなにか? 私はその人の人間としての自律性を奪ったのである―その人がこっちへきたのに、私はなぐりつけてあっちへ行かせたのである。これが真の暴力行為の本質であるように私には思われる。暴力は、人間からその自律性と選択の自由を奪うところにある。この意味からすれば、いま用いられている暴力の大部分は、実際には真の暴力ではないことになる。一時の暴力であるかもしれないが、長期の暴力ではない。ブレヒトが一体化への傾斜を妨げるとすれば、観客がある方向に行くのを阻止していることになる。彼は観客の前に手をあげ、「止まれ!」と言っている。その意味で彼は、観客に対して一時の暴力を用いたわけである。しかしながら、彼の究極の目的は、少なくとも彼の言葉を信じれば、観客がその状況について自由に自分の結論を出せるようにしておくことであり、したがって彼が個人としての自律性を保とうとしているがゆえに彼は暴力を用いてはいないのである。一方、観客をある方向に押し付けるストリップ・アーティストや政治的プロパガンディストは、観客の自律性と自由な選択を奪い、ある種の行動を強制するがゆえに、真の攻撃行為を犯している。『ユダヤ人ジュース』の観客が、見る前にはなんの悪意もない家庭の主婦たちであったのに、家に帰って「ユダヤ人はみんな殺すべきよ」と言ったとすれば、彼らは自動人形に、彼らの心理反応をあやつるものの奴隷に、変えられてしまったのである。これが演劇における暴力の正当な使用と不当な使用を区別するものである、と私は思う。
暴力が観客の世界に対する自覚を高めるように用いられ、観客に与えられるショックが自分のおかれている状況の現実をいままで以上に評価できるようにするものであるならば、その暴力は正当に用いられたのであり、倫理的に擁護しうるものである。暴力が観客の自律性を奪い、それがなければしたいとは思わなかったであろうような行動を強制するものであるならば、それは不当である。
(250-1 マーティン・エスリン「現代演劇における暴力」『現代演劇論』小田島雄志訳 1972年)
關 個人的には、演劇が持つ暴力に正当も不当もないと思います。ここでエスリンが論じている二つの暴力は容易にどちらかになり易く、その境界線は流動的です。ただ、演劇がある種の影響力を観客に与えるとし、それをアルトー(Antonin Artaud)を持ち出して「暴力」であるとしている点は興味深いです。というのも、ここには少なからず現代演劇、特にイギリス演劇が「暴力」と「残酷」と「乱暴」に共通点を見出し、若干混同していることが見られるからです。私は暴力(violence)、残酷(cruelty)、乱暴(rough)は別の文脈にあるものだと思います。アルトーの残酷をちゃんと理解しているとは言い難いですが、彼はより祭儀的なものに近寄って行くのに対して、現代イギリス演劇の多くは暴力を政治的に用いています。また、乱暴は肉体や精神に対する暴力行為を舞台上で再現することを求めるようなものに対して用いられ、それは残酷と直接的な関係があるわけではありません(確かにアルトーの作品には暴力行為の描写は多いですが)。…というのが私の意見ですが、このエスリンの持っているような考えは2000年以降もイギリスの演劇研究者の中に見られますし、検証は必要です。
鹿島 《暴力》は今回の劇でも、というか演劇という他者性を多分に伴った集合藝術において、常に問われる重要な要素だと思います。これが舞台上でどう扱われているのか、再現や代理表現として露骨に具体化しなくても、観客の皮膚感覚的にどう感じ取られているか監査していく必要がある。同時に、何に対する《暴力》として表出されるのかということについて、選択していくことが求められるだろうなと。
「何か「ことば」にしてしまうことで失われていくものがあって、しかし「ことば」で表すしかない、何かを失わせるその力を「暴力的」と表現した」という視点について、一例として「花」という言葉を発語したあとにプロジェクターなどで実際の花を映写した際に喪われるものがあったりしますよね。この手法自体のベタさは別として、自分なんかはロベール・ブレッソン的なイメージの限定力を想起します。観客の自由な想像力が損なわれるという意味では《暴力》的なんですが、カトリックのような一義性の羅列による限定の力には、ある種の思想性を感じたりもします。イェリネクにとっての《暴力》というのもありますが、イェリネクのテクストにどんな《暴力》を持ちこんだらもっと面白くなりますかね?
イェリネクの文体は、気を抜くと言葉の神秘性に舞台上がどんどん呑み込まれてしまう危険性があるように思います。關さんが翻訳してくれた作家のインタビューで惹かれたのは、サイモン氏がイェリネクの作家性について「ぼろぼろになるまで使い果たす」という言い方をしている点ですね(ベケットの《消尽》という言葉が頭をよぎりました)。イェリネクが「観客については少しも考えていません。それでもやはり私の作品は集団向けだと思います」といってのけたあとに、「ダイアローグとは異なる形式を見つけなければ」と考えているのが興味深く、『雲。家。』のテクストがいっけんモノローグとして読めてしまうようで、単純なモノローグに納まらないものを志向している、ということにどう付き合えばいいかなと思います。それをバフチン的な意味での《ポリフォニー》と言ってしまうには、少し穏やかすぎるんじゃないかと。以前、直感的にコロスという言い方で留まった理由にも繋がるんですけど。
では、どんな対立構造が必要なのか。ヨッシ・ヴィラーのような世俗性に依拠した(既存の演劇的事象としての)関係性を舞台上で《再現》してあげればいいのかというと少し躊躇がある。また逆にベケットの『私じゃない』のように、「わたし」と「わたしを否定するわたし」のような対立、分裂症のように一元的な自己が内部分裂している構造を演劇化することがふさわしいかというと、それもどうかなと。どうもイェリネクが言っている「集団向け」という言葉には、独特な集団の在り方を前提としたダイアローグ?/モノローグ?が希求されているように思うんですね。外部に向けての対立や内部に向けての対立といったような、固定された空間で一方通行なものだとはちと考え難い。
ここで演出として苦しいのは、まだ空間的な軸がよく見えてこない点。たとえば、かつてコロスには、凄惨な事件を聞きつけてテーバイの館の前に集結した人々(そのまま客席に座る人々の代弁/傍聴席的な時空間への接続)という、いわば境界に立って客席と舞台上を繋ぐ、《多声》を増幅させる装置としての空間的役割があったと思うんですね。ヨッシの演出にも遺物(テクスト)と関わるという空間を軸にして、歴史の深淵に降りる/降りられないを演じてみせた。『私じゃない』では、俳優の身体で収斂されるはずの一元的な自己を俳優自らが打ち消していくプロセスを、身体という空間を軸に展開しています。高山明さんの作品を藤井さんが「から」としての身体として読み取っているのは面白い指摘だと思っていて、身体という空間が《家》としても読めるようになっていた(抜け殻としての衣裳という美術は同様のコンセプトからでしょうか)という構造は、『私じゃない』の換骨奪胎的な空間性だったのかなとも。一人で上演しているというのも共通していますね。自分が去年京都で上演した時は、劇場空間にテクストを空虚に響かせたわけですから、そういう意味では高山さんの《からの身体》を劇場空間に拡大してみせたものであったんだなと思います(いま書いていて整理がつきました笑)。
さて、自分の演出としての始め方としては、観念で演劇を立ち上げないように気をつけることなのですが、それは同時に「いま手元にある条件から、演劇を思考する」ということを一つの縛りとして取り組んでいることでもあります。そうすると、6人、少なくとも舞台上に6人の身体が在る、という条件とテクストの繋がりを見出さなければ、つまりイェリネクの志向性としてあった「集団向け」という問題に6人の身体という条件から取り組まなければならないと考えています。同時に、演劇であることを忘れない遊びとして立ちあげることも。
書いていて、空間でふと思いついたのは、「ダイダラボッチ的空間(+雲)」と「からの身体としての劇場空間」と「《わたし》の見える空間」の三つを舞台上に立ちあげることですかね。複数の空間を立ちあげるとなると、美術と照明さんが大変そうですが、雲とか最初は地面すれすれで、テグスとか使って途中で空に飛んでいってくれたりすると面白いかも。ちょっと寺山で使った「場を仕立て上げる演劇空間」の延長にありますが。巨視とか微視とか、ロバート・ウィルソン的な運動と工事現場的なごちゃごちゃ感があると面白いかも。どっちか一方だと構成美や猥雑さに納まってしまうので。いずれにせよ、6人が一元的な場としての空間にいることを選択するのか、多元的な場としての空間にいることを選択するのか、随分テクストの聞こえ方も変わってくるように思います。ひとまず、今日までの稽古を通じては後者の可能性を模索する作業に入っています。
最後にもう一度、この話の発端になっている《暴力》に触れて一先ずお返しします。
關さんには、ぜひ他のイェリネクのテクストにある《暴力》のバラエティーを調べて投げてもらいたいのですが、エスリンの「暴力は、人間からその自律性と選択の自由を奪う」という考えは、現在の観客が持つ《承認願望にも似た参加欲求》と照らし合わせても面白い視点だと思います。つまらない芝居だと、物語が進行することだけでも《暴力》になりかねないくらい概念の拡張が著しい問題じゃないかと。その上で、今回の舞台でどんな《暴力》を行使するのか、考えないといけないですね。その際には、いまパッと考えたかぎりではイェリネクの作家性やテクストに寄り添ったものと、そうではなく僕らが持ちこむ演劇性としてのものと、大きく分けて二方向からのものがあるかな。双方からのアイデア求めます。
余談ですが、イェリネクのテクストを俳優が捲し立てて喋るというやり方を、よく目にしますが、あれも最早パターン化した《暴力》の一形式だと思うのですが、どうなんでしょうねあれ。必要な《暴力》なんでしょうかね?
(2012/09/08 往復の記録)
《エルフリーデ・イェリネク Elfriede Jelinek 1946~ 》
オーストリアのウィーン出身。ドイツ語圏を中心に活動している小説家・劇作家・詩人。「オーストリアで最も憎まれる作家」として名高い。ウィーン市立音楽院にてオルガン、ピアノ、フルート、作曲を学び、ウィーン大学では美術史と演劇学を専攻した。74年カトリック教会を脱会しオーストリア共産党に入党、91年まで所属。04年のノーベル文学賞を含め、様々な文学賞・戯曲賞を受賞。主な著作に、ミヒャエル・ハネケ監督によって映画化もされた小説『ピアニスト』(83)をはじめ、『したい気分』(89)、『トーテンアウベルク』(91)、『死者の子供たち』(95)などがある。またトマス・ピンチョン『重力の虹』の翻訳にも挑戦している。社会の保守性によって隠蔽された性差の歪みや死者の声を暴露的に描き出す小説家として知られる一方で、様々な古典的文献からの引用やパロディ、断片的な描写の列記から生じるイメージの飛躍を織込んだ文体によって、演劇の《上演可能性》そのものを問う劇作家としても注目されている。本公演で取りあげる『雲。家。』(88)は、西ドイツのボン劇場にて初演され、奇しくも翌年の東西ドイツ再統一を予見した作品となった。
Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.