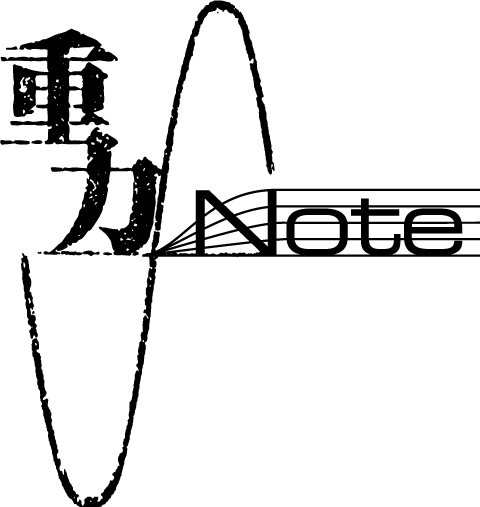▷Project
夏目漱石は当時の世界中を覆いつつあった《近代化》の波を前に、日本人として文字通り最初に肌身を持ってたじろいで見せてくれたハムレットのような存在だった。「仮に百年の後に漱石が残るとしても、彼は『草枕』や『坊つちゃん』の作家として残るのではさらにない。彼は、作家でもあった文明批評家として残る」と、批評家の江藤淳が予告しているが、《近代化》か《植民地》かという選択肢を迫られた明治の変革期における日本人の、感覚の逍遥に言葉を与えていくことのできた作家だったのではないか。
『吾輩は猫である』における有名なフレーズ、「吾輩は猫である。名前はまだない」は、猫の視点から人間社会を眺めるという構造を端的に表した一節だが、「吾輩は《日本人》である。名前はまだない」と置き換えて展開していくことで、漱石から百年以上経った現代の日本において、国内外にある未だ名づけられていないものや感覚を演劇化することを目指した。《日本人》自らのアイデンティティを切り開いていく時間としての演劇を、夏目漱石のテクストから取り出す試み。
第20回BeSeTo演劇祭BeSeTo+参加作品
▷あらすじ
《誰か》がいる。彼は寝そべる。右手を左胸の上に乗せる。「私は貴方がたが自由にあらんことを切望するものであります。」彼は何か満天の星でも眺めているような様子で、ぼんやりと天井を眺める。また別の《誰か》が現れ、何かを観察している。別の、また別のと《誰か》たちが現れ、何かを眺めている。彼らは、ぼんやりと一点を眺める。そこには日本一の名物があるらしい。「あなたはどちらへ」「東京」彼らは何かしらのもの、言葉を眺めている。もしくはそれは記憶と呼ぶべきものかもしれない。『三四郎』、『それから』、『硝子戸の中』、『吾輩は猫である』…。世の中が大きく動いた時代、世界と日本と私についてとことん考えた作家・夏目漱石。そのテクストが抱え込んでいる無数の《眼差し》を立ち上げていく《誰か》たちの物語。








会場 アトリエ春風舎
原作 夏目 漱石『三四郎』ほか
戯曲 市川 タロ(劇作家・『デ』代表)
出演 瀧腰 教寛 立本 夏山 平井 光子 邸木 夕佳
構成・演出 鹿島 将介
舞台美術 深代 満久
衣裳 富永 美夏
照明 安藤 直美
音響 佐藤 尚子
音響操作 永井 彩子
演出助手
ドラマトウルグ 佐々木 琢
翻訳協力 伊藤 羊子
宣伝美術 青木 祐輔
制作 本多 萌恵
協力 夏山オフィス アトリエ春風舎 にしすがも創造舎
宇野 敦子 三枝 淳 菊池 徹也 築地 静香 中江 俊介 中村 みなみ 根岸 佳奈子 針谷 あゆみ
しおり協力 姉川書店 アトレ吉祥寺東館店 カモカフェ 紀伊國屋書店新宿本店 小宮山書店 澤口書店
書泉グランデ ジュンク堂書店池袋本店 ジュンク堂書店吉祥寺店 大雲堂書店 代官山蔦屋書店
大盛堂書店 バサラブックス 模索舎 パルコブックセンター渋谷店 パルコブックセンター吉祥寺店
ブックセラーズ西荻 ブックファースト 明倫館書店 山下書店渋谷南口店 リブロ池袋本店
MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店 Paper Back Cafe-東京堂書店 TSUTAYA三軒茶屋店
後援 新宿区
助成 アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)
提携 (有)アゴラ企画・こまばアゴラ劇場
共催 第20回BeSeTo演劇祭実行委員会
主催 重力/Note


カブトと《平凡》の居心地
もう随分前になってしまったけれど、お札の肖像にあわせてカブトに折り紙するのが流行っていたことがあった。稽古場でも、流行に付き合いのいい女優が器用な手つきでテキパキと折りたたみ、あっという間にカブト姿の漱石を作ってくれたのだが、どこかキョトンとした眼差しのその姿は、背広やネクタイとのアンバランスさとあいまって、いかにも居心地の悪そうな感じだった。それでいながら、妙に納得するものがあったのを覚えている。
書き記した言葉に触れてもらうことを本分とするのが作家だとすると、漱石と私たちのあいだには、他の作家たちとは大きく事情が異なるものがあるように思う。日本で生きていくなかで、「必ず読む機会を用意されている作家」という意味では、長らく国語の授業の中で取りあげられてきた漱石は、誰もが一度は読む作家だった。また日常生活において、最も取引される銀行券の肖像としても強い印象を残しているということからも、私たちが毎日顔をつきあわせてきた作家と言ってもいいのかもしれない。
寺山修司が噂話によって実像が拡散していった作家だとすると、漱石は教育や通貨といったシステムによって実像が空洞化されてきた作家じゃないだろうか。フェルナンド・ペソアも母国ポルトガルで同じ憂目にあっているが、作家にとっての死後の栄光というものには、マスコット化されて愛でられる一方、その精神が宿っている言葉それ自体からは人々が遠ざかっていくという皮肉が伴われるらしい。ここには《国家》と《個人》、それらを仲介している《社会》との結びつきをめぐる皮肉なドラマがある。
それにしても私たちは、一体何を漱石という存在に依託してきたのだろうか。最近では教科書から外れることもあるようで、漱石が千円札であった記憶も次第に遠のいてきた。近代以降の日本人が、常に漱石の言葉を傍らに置き続けた意味について、そろそろ考えてみたいと思っている。《平凡》と感じるくらいの距離感にあるものほど、最も根深い問いを抱え込んでいるはず。出る杭を打ってきた日本においては、尚更。
鹿島 将介
▷戯曲作者より
感傷と恥じらいの間でよく揺れる。男は夢を見るものだ。猫は虎になる夢を見る。代助は眠りの最中に花の落ちる音を聞く。それから、女が起こしにくる。夢のなかにいつまでもいることは難しい。
漱石の言葉を借りて文章を書く。別にそれは自分の言葉でもなければ、実のところ漱石の言葉でもないのだろう。書くことは他人を欲望することだからだ。
書くことと読むことの自律性は性交と出産に似ている。戯曲は変だ。書くなかで発音に至るまでを考える。妊娠の不安を抱えた性交のような後ろめたさがある。
書くことは他人になろうという無限の試みだ。自分からの逃亡、自身を喪失しようという欲求だ。だからロマンティックな人間は自殺する。芥川は死んだ。漱石はというと、いつも女が起こしにきてくれた。起こされたら、起きねばならない。それが漱石という人の流儀なのだろう。
市川タロ
▷演出より
いよいよ《日本人》がわからなくなってきた、と思ってみる。ちょうど一年前、BeSeTo演劇祭での上演を企画したとき、《日本人》を切口にするならばと候補にあげた作家は三人いて、小泉八雲、宮本常一、そして夏目漱石だった。
作家を取り上げるとき、《何故いま〇〇なのか?》というお決まりの問いを立てたりするのだけれど、テクストが持つアクチュアリティや大文字としての破局的な切れ目よりも、生活の傍らで小さく燻っている破局、生存感覚が揺らいでいくものに眼を向けるようになってきたから漱石になった、としか言いようがない。
いや少し嘘をついた。ここは漱石だと実は確信している。長らく私たちは《国民的作家》という称号を与えて漱石を安全なもののように扱ってきたが、それは同時に彼が思考したことの痕跡を反復していくことを、私たちは無意識的に選択してきたとも言える。生きていくために様々なフィクションの在り方を必要とした、ひとりの日本人の姿を通じて、「いま私たちが信じられるもの」について考えてもらえたらと思う。このことは、演劇というジャンルそのものにも向けられるに違いない。
鹿島 将介
▷【夏目 漱石 Souseki Natsume 1867〜1916】
日本の小説家・評論家・英文学者。江戸・牛込馬場下横町出身。本名は金之助、俳号を愚陀仏とした。名主として知られた夏目家に生まれるもすぐに里子に出され、姉に連れ戻されたものの塩原家に養子に出される。養父母の離婚により9歳から夏目家で育つことになるが、復籍したのは21歳だった。帝国大学英文科を卒業後、松山や熊本での教員生活を経て33歳の時にイギリスへ官費留学。しばらくして神経衰弱になるとともに下宿を転々とし、「漱石発狂か」と噂されるなか帰国。小泉八雲の後任として東京帝大で教鞭を取るも不評。同時期に勤めた第一高等学校では、漱石に叱責を受けた数日後に華厳の滝で自殺する生徒がいたりと、再び神経衰弱に陥る。高浜虚子の勧めで精神の治療がてら『吾輩は猫である』を執筆。続く作品群も好評を得たことで一躍人気作家へ。1907年には教授職を断って朝日新聞社専属の作家になった。「修善寺の大患」以降は、死を意識するようになる。一方で多くの門下生を世話し、彼らを意識して書かれた作品も多い。活動期間は約10年間、日本語が近代化されていくプロセスを体現した。代表作に『坊っちゃん』『三四郎』『こゝろ』、絶筆に『明暗』など。旧千円札に肖像があったのは記憶に新しい。
Related Projects
▷ポストトークゲスト
【川口智子:演出家・劇作家/座・高円寺 企画・制作スタッフ】
佐藤信の個人劇団「鴎座」で活動。ベケット作品の新訳上演や、サラ・ケイン『Cleansed』の連続上演「クレンズドプロジェクト」を企画・演出。多様なジャンルのアーティストとの長期的なワークショップによる作品づくりが特徴。2013年12月には、ケインの幻の作品を題材に新作 『Viva Death』を上演。
【広田 淳一:劇作家・演出家/アマヤドリ主宰】
2001年、東京大学在学中に「ひょっとこ乱舞」を旗揚げ、主宰する。以降、全作品で脚本・演出を担当し、しばしば出演。さりげない日常会話ときらびやかな詩的言語を縦横に駆使し、身体性を絡めた表現を展開。随所にクラッピングや群舞など音楽・ダンス的な要素も節操なく取り入れ、リズムとスピード、熱量と脱力が交錯する「喋りの芸」としての舞台を志向している。簡素な舞台装置と身体的躍動感を中心に据えた必須としながらも、あくまでも相互作用のあるダイアローグにこだわりを見せる。(『ひょっとこ乱舞』は2012年から『アマヤドリ』として活動しています。)
【市川タロ:劇作家/ユニット・デ代表】
1989年生。東京出身、京都在住。劇作家、演出家。2011年、ゲッケン・オルタナ・アート・セレクションへの選出を契機に、自身のユニット・デを立ち上げ、劇場に限らず野外、ギャラリーなどでの作品を発表。作品に、6時間のインスタレーション作品『ルーペ/側面的思考法の発見』(Gellary Near)、北園克衛の詩を用いた移動演劇『きれいなハアト型』(京都市立芸術大学学内)、安部公房『S・カルマ氏の犯罪』をモチーフにした会話劇『名づけえぬもの』(STスポット横浜)など。
【佐々木琢:劇作家・演出家/王子小劇場プロジェクトディレクター】
座・高円寺劇場創造アカデミー舞台演出コース修了(1期生)。演出家 川口智子がサラ・ケイン『Cleansed』を連続上演する「クレンズドプロジェクト」、重力/Note『雲。家。』などで演出助手を経験。盛岡で行われた「名作を読もう!『走れメロス』」では脚本を佐藤信と共同で担当した。2012年8月に初の作・演出作品『口をあけて寝ている』を上演。
▷しおり作成&配布
演出助手の永井彩子による、演劇と読書をつなぐ試みとして生み出された「偽造/夏目漱石」のしおり。
快くOK出してくれたお店のご紹介をSNSでまとめました(▽画像をタップすると読めます)。
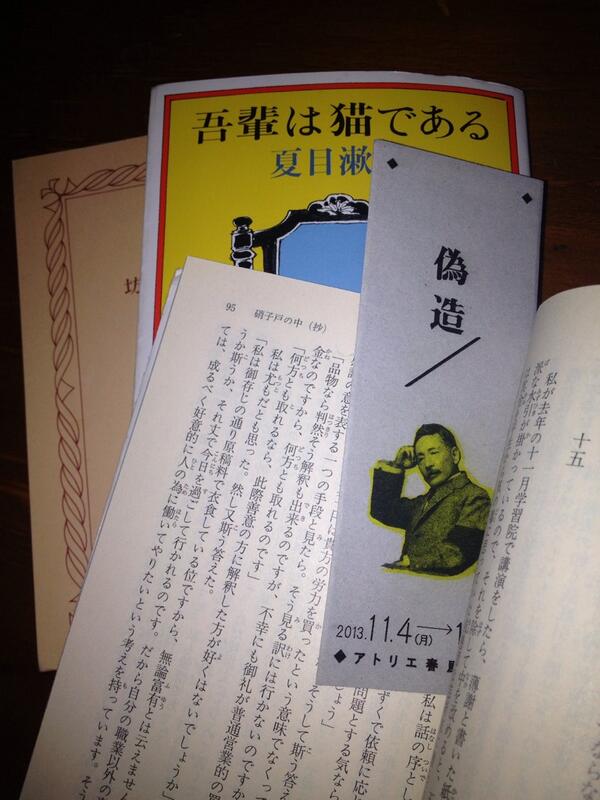

Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.