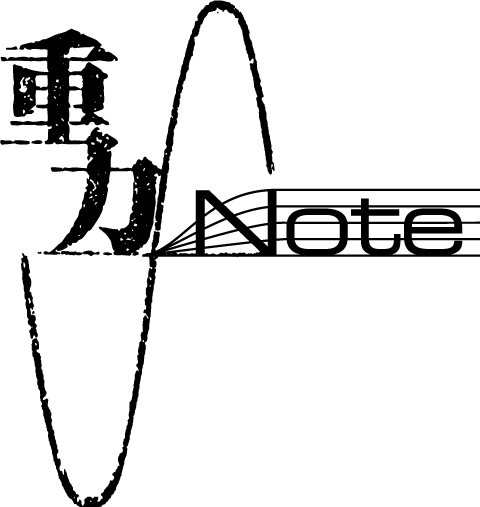『ドラマ・モラリア』は、鹿島が学生時代から2009年にかけて演劇を支える原理と倫理を素描しようという意欲から断章の形式で始められた。ここにあるNo.1〜37は、当時書き記したメモから抜粋されている。その後、SNSの普及により短文的な気づきはここに編纂されなくなってしまい、頓挫したままとなった。表現活動を重ねる中で考え方も随分と変わってしまってはいるのだけれども、十代から二十代前半の直観が捉えたものは忘れた頃に思いもよらない驚きをもたらすかもしれないので残してある。こうした言葉群によって突き動かされた人間がいた、ということで十分かもしれないのだが。
(2022.05.13.)

1
難しいことはいらない。演劇が起こるためは、目の前の空間に意図された時間が流されればよい。ただ、その前にそれらを知覚しようとする観客を存在させなければならない。これらは俳優によって形成され、保証されるものである。俳優は時空間と知覚の保証人でなければならない。
2
演劇は限られた空間の中に意図された時間を流し込む芸術である。よって演劇は時空間を発見しないかぎり、始まることはない。たとえそこに俳優がいて、その周りに観客が取り囲んでいようとも、そこに時空間が発見されない限り俳優は俳優ではなく、ただの人の形をした予定調和な機械に過ぎない。「なにもない空間」の中で俳優が演技を始めれば演劇であった時代は終わった。演劇は時空間を発見し、それを造形していかなければ成立しない。その作業は、まず劇作家によって志向され、演出家によって設計され、俳優によって構築され、観客によって知覚されなければならない。時空間の構成の在り方次第では、俳優すらも必要としない瞬間もあるだろう。
3
演劇とは〈喪われた経験の回復〉である。〈経験の古典〉を読み解くこと。人類の経験のリストを一つ一つ開示していくこと。我々が暗黙のうちに経験させられているカタストロフィを再起させること。その時、虚構は唯一の救いとなるだろう。
4
「経験ということは、たしかに人間には必要だと思うのですが、どんなに経験しても、人間というものはその経験を想像力のなかで造型できなかったら経験にならないわけです」(安部公房)
5
我々は虚構(フィクション)という概念を取り違えてしまっているのかもしれない。現実(リアル)から逸脱したものを安易に全て虚構(フィクション)と呼んでやしないか。はたして虚構は本当に現実と対置できる代物なのだろうか。
6
虚構(フィクション)は日常から乖離した特殊な状態にあるものだと言われる。しかし一方で、実感だとかリアリティだとかいった感覚もまた、恒常的なものではなく、むしろ非日常的なものだといってよい。
7
虚構の精神史というものが存在するのかもしれない。虚構の精神の変遷。これはリアリティの変遷と深い繋がりがあるのではないか。
8
生命が生命である限り向き合い続けるリアリティと、人間が人間である限り向き合い続けるリアリティと、その同時代精神ゆえに同調できるリアリティとがある。それぞれの交叉する地点を思考すること。その際に働く科学的な歴史認識。
9
舞台という場所がどこにあるのか、を考えてみる。
10
「動体の上で、動きかつ動かす建造物を打ち立てる建築術以上に感性の鋭い建築術はない。」(ヴァレリー『海への眼差し』)
11
人のはじまりの形は円である。それが社会という名の岩間へと叩きつけられた瞬間、歪な形へと変貌する。人は一生かけてそれを元に戻すのである。
12
現象としての演技から、それを支えているこころのかたちへ。
13
演技はもはや消費されている。この現実を前に、俳優は選択すべきである、ジャンルの奴隷になる道を選ぶのか、それともジャンルを発見し続ける道を選ぶのかを。
14
名優になってはならない。人間存在を顕在させる司祭たれ。
15
「舞台上で何をすればいいのか」という問題意識から「どんな時間を生きているのか」という問題意識へ。
16
時間芸術としての演劇―今、どんな時間が流れているのか自覚的に構成すること。時間の質を変化させていくこと。観客にどのような時間を体験させるのか。また、俳優がどの時間を生きているかを眺めさせるか。
17
時空間とは社会であり、世界である。それは同時に身体でもある。
18
演技は劇社会を導く。劇社会の人々が現実社会の人々と出会う時、決して触りあえない実感の中で、劇社会は私達の前で崩壊してみせる。その崩壊の規則性を陰画としながら、コミュニケーションの不可能性を印象づけて瓦礫となる。瓦礫の前で私達は呆然としなければならない。
19
技芸は何故生まれたのか―技芸はかつて曲芸の延長線上に位置するものであった(特権性の獲得)。また、表現様式の固定化に伴う型としても存在していた(ここには一座の教育上での問題もある)。いずれにせよ、技芸は目に見える〈特化〉を志向していたと言えよう。言い換えるならば、技芸は根源的には〈俳優がよく見えること〉を志向していたと言える。だが、そのことは同時に技芸による〈隠蔽〉を構造上、避けられない傾向として内包していたことを意味する。つまり、見えないものが見えなくなることの隠蔽―。
20
メソッドとは、それがそのまま俳優の思考回路を形成できるものでなければならない。筋トレ的なものやテクノロジックにツギハギするようなものではないということ。俳優が「何故この運動をするのか」という問いを立てることができ、またそこから生じる一つ一つの課題を明確にクリアしていくことを可能にすること。
21
固定点は身体と想像力が帰着する場所である。およそ第三者によって知覚できる変化とは固定点の流動においてである。では固定点とはどこに生まれるものか。それは意識が宿る場所に生まれるのだ。
22
意識はイメージに乗る前に物理に対して誠実にならなければならない。物理を見失った意識は嘘をつく。意識は嘘をついてはならない。
23
制約(ルール)の数と緻密さを眺めること―それが表現の強度と豊かさに通じている。しかし、またこのような眼差しも必要であろう―何が表現によって救出されているのか。
24
俳優は訓練を通して己の身体を表現体として取り入れるとともに、そこに表現者としての精神を形作るアンサンブルを見出さなければならない。表現者としての精神は、社会的立場や個別の自己が保障するものではなく、その一連の行為の中にのみ存在する。そして、その行為から「ジャンルなきジャンル」である演劇の中に一つのジャンルを思考する時、俳優は存在するのである。
25
像から動きへ。形から変形へ―我々の身体は目鼻立ちや背格好など個別的なものである。しかし、行為における働きかけに対しては、画一的な認識の下に行なわれるため、異質性や差異は表出されない。その際に表出されるのは、あくまで日常生活上の〈生な身体〉の癖にすぎない。異質性や差異を含まない個性は、個性ではない。このことは運動に対する意識が同じである限り、異質性や差異は知覚されないということである。
26
セリフを覚えないでおこなう即興は、常に遊戯性を超えて戯曲に対するパロディになりうる。
27
即興とは、単なる「思いつき」の速度感を見せることではなく、瞬時に如何に多くのルールの上を歩いて見せるか、ということだろう。
28
様々な演劇的な虚構に対する構成力及び編集能力―演劇的知性。
29
言葉は一見凝り固まった一般的な意味の総体である。しかし、一度その中身を引っくり返したならば、再びどのように詰めなおすかという地点から始められる。その時、何を選び何を棄てるか。この作業を通してその言葉の一般的な意味と拮抗することで、言葉はその生命力を再び持ち得ることになるだろう。
30
存在するとは、その周りを取り巻くあらゆる物質の中で孤独になる、ということである。
31
舞台における存在論とは、意識的な存在を舞台にあげるというよりも、存在から無意識を可視化させることによって成立するのではないか。
32
テクストとは既に一度死を迎えた遺骸である。
33
記号化されて追いやられてしまっているものを解体すること―特に動詞の現在形を描くこと、もしくは動詞の発明。
34
演出家とは、俳優の身体を通して生まれた身振りに対して、観客の知覚にどのような変化が起こるのかについてしっかりと観察するフィールド・ワーカーである必要がある。
35
再起される経験としてのテクスト。
36
「オリジナル・テクストは翻訳され、解釈されることで、はじめてテクストとして生成する」(ベンヤミン)
37
写真によって発見された人間の無意識―演劇が写真技術によって発見した領域とは何か? ビオメハニカの発想は映画のコマ送り(連続写真)から発してはいないか。知覚の拡大によって発見される人間存在の在り方が新たな技術を生み出す。知覚の変遷と技術の変遷は密接である。

Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.